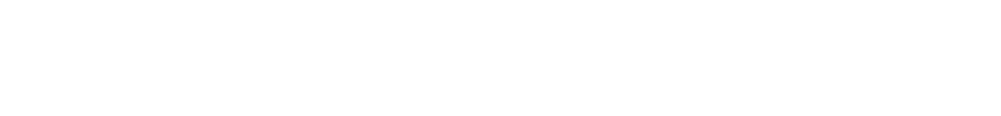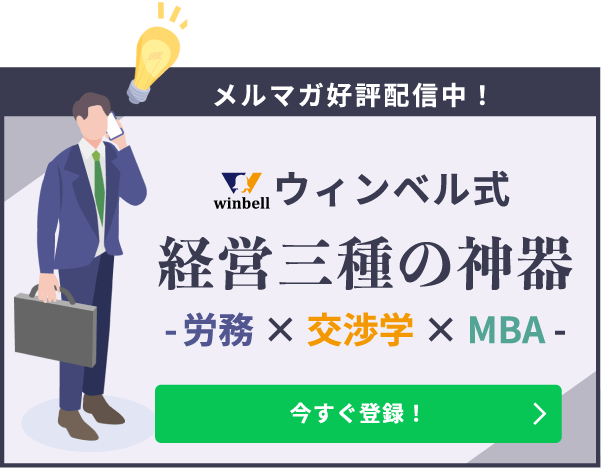退職代行〜円満退職のためには〜
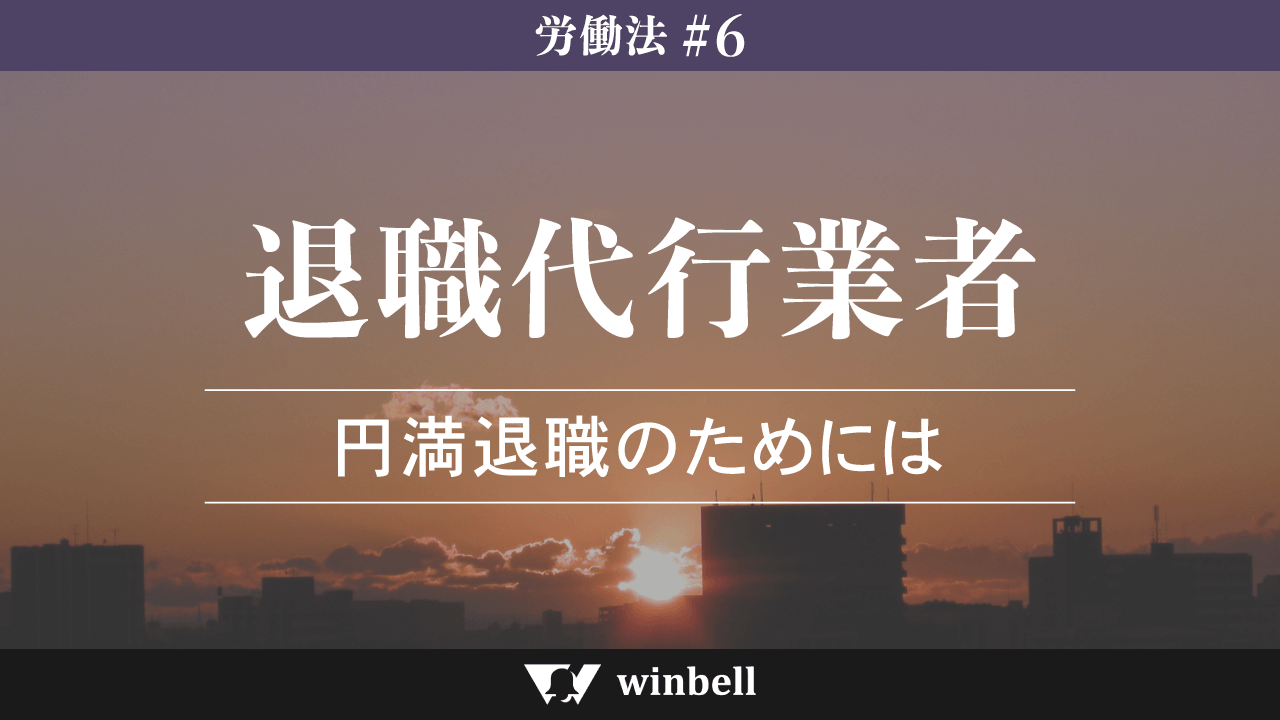
皆さんこんにちは、弁護士の山口真彦です。
本日も経営者のための労働法講座をやっていきたいと思います。
最近よく耳にする退職代行業者
最近、経営者の方から退職代行業者に関するご相談を非常に多くいただいております。
そこで、今回はこの「退職代行業者」をテーマにお話をしようと思います。
具体的に経営者からどのようなご相談が多いかというと、一番多いのは、「退職代行業者から突然連絡が来た際、会社としてどのような対応をしなければならないか。」というご相談が多いです。
その他、退職代行業者を使ってほしくないと思っている経営者の方が非常に多く、「従業員に対して退職する際に退職代行業者を使ってはいけないというルールを定めることはできないのか」というご相談も多いです。
今回はこの2つに絞り、退職代行業者について書いていきたいと思います。
退職代行業者を従業員に使わせないことはできるのか
まず、 従業員に対して退職代行業者の使用を禁止させることができるのかという点です。
もし、禁止する場合、その方法としては、
- 就業規則に退職代行業者の使用禁止を明記する
- 個別の労働契約・雇用契約の中に退職代行業者の使用禁止を明記する
等になるかと思います。
では、退職代行の使用禁止を明記しても、従業員が退職代行業者を使ってきたとなった場合に何かしら会社として対応ができるかという点です。
結論から申し上げると、就業規則や個別の労働契約・雇用契約の中に 使用禁止という規定を明記していたとしても、退職代行業者を従業員が使ったときにそれを拒否するということは、法律上は難しい。というのが私の考えになります。
というのも、退職の手続きで退職代行業者の使用を禁止すると就業規則等で定めていたとしても、退職代行業者を使う場合には退職は認めないという話をするのは、なかなか難しいです。
また、退職代行業者を使うということは、従業員側は辞める決意をしっかりしていることになります。それを、業者を使っているという理由で辞めさせないというのは、法律では難しいところです。
就業規則や個別の雇用契約・労働契約の中に 退職代行業者を使ってはいけないと明記することは、従業員に対する牽制の意味では効果があるかもしれませんが、法律上では有効とは言えないと思います。
退職代行業者からの連絡がきたら
次に、退職代行業者から実際に連絡が来た時にどのように対応すればよいのかという点です。
こちらは、経営者としてどのように考えるべきかというところですが、私の個人的な考えとしては、退職代行業者が入るということは、第三者が入るということになります。第三者なので、お互い冷静に感情的にならずに話を進めることができます。
逆に、退職代行業者を活用してみてはどうでしょう?
会社側は、逆に退職代行業者をうまく活用すればいいと思います。
実際に退職代行業者から連絡があると、意外と会社側は、辞めたいと言っている従業員に対して、引継ぎ事項等必要なことを従業員に伝えやすくなります。
会社側が伝えたいこととして一番多いのが、業務の引き継ぎです。
例えば、辞めようと思っている従業員が担当していた顧客について、その従業員しか知らない情報があった時に退職代行業者に対し、この情報を本人に教えてくださいと伝えてほしいということができます。
意外と退職代行業者は素直に対応してくれます。
辞めた後の業務が円滑に進められるという意味では、業務の引き継ぎは絶対必要になってくるので、逆に退職代行業者を使者として上手く使うことがポイントだと考えます。
当事者間で話をすると、辞めたいと思っている従業員が「会社に迷惑をかけてやろう」と感情的になってるかもしれません。
そういうことは避けたい場合に、第三者である退職代行業者をこちらも上手く活用したほうがよいと思います。
退職代行業者から連絡が来た時に経営者・会社側は「大変だ…。」と思わず、円滑に退職手続きを進められるように退職代行業者を上手く使って、業務の引継ぎを進めた方がよさそうです。
従業員はもう辞めようと思っているので、そういう人を引き止めることはなかなか難しい話です。
その人がやめたとしても会社の業務運営がスムーズに行くように対応するほうがいいと思います。
経営者側からすると、最後くらい自分の口できちんと話して、業務の引き継ぎもしっかり行ってから辞めてほしいというのが本音だとは思います。
退職代行業者を使うことに対してネガティブな印象を抱いている経営者の方も多いと思いますが、使用を禁止するということはなかなか難しいです。
もし、退職代行業者から連絡がきたとしても、前述のとおり、逆に活用するくらいの気持ちで対応していただければと思います。
大切なのは就業規則を工夫すること
退職代行業者を使ってはいけません。と明確に就業規則に明記することは、法律上の効果はなさそうとお伝えしました。
しかし、就業規則の退職規定をうまく作ると、従業員が退職の意思を早めに伝えてくれて、時間の余裕を持った業務の引き継ぎも対応してもらえるようになります。
就業規則の規定を工夫さえすれば良いので、退職代行業者を使うなと書くわけではなく、別の文言をうまく使うことによって、会社と従業員がお互い気持ちよく対応できる就業規則作りをすることもできます。
今回、退職代行業者に関する内容でしたが、従業員に円満に退職してもらう・業務の引き継ぎもきちんと対応してもらうために、どのような就業規則を作れば良いのか、そういう視点で今一度、自社の就業規則の退職規定の部分を見直してほしいと思います。
そして、ご自身の会社の就業規則について確認してほしい、問題のないものに改定してほしいということがございましたら、ぜひウィンベル合同会社にお問い合わせいただければと思います。
最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。