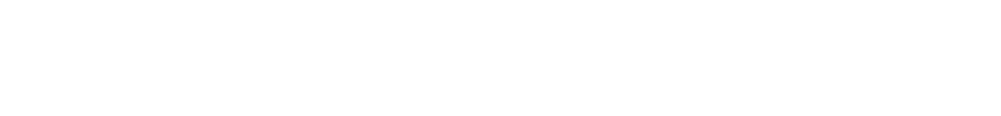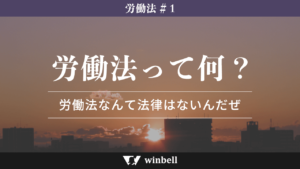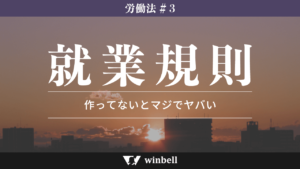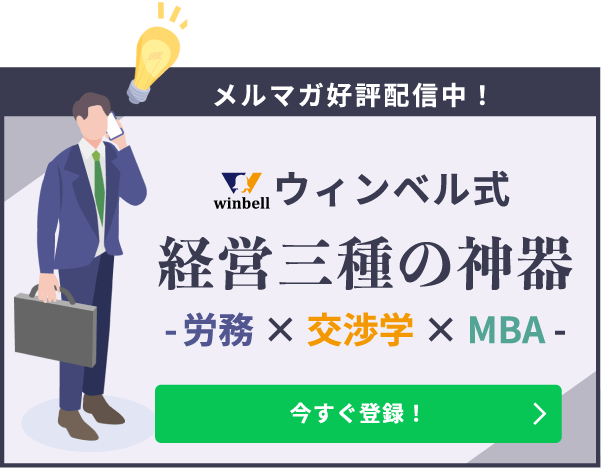労働者とは~その業務委託先は本当に「労働者」ではないのか~
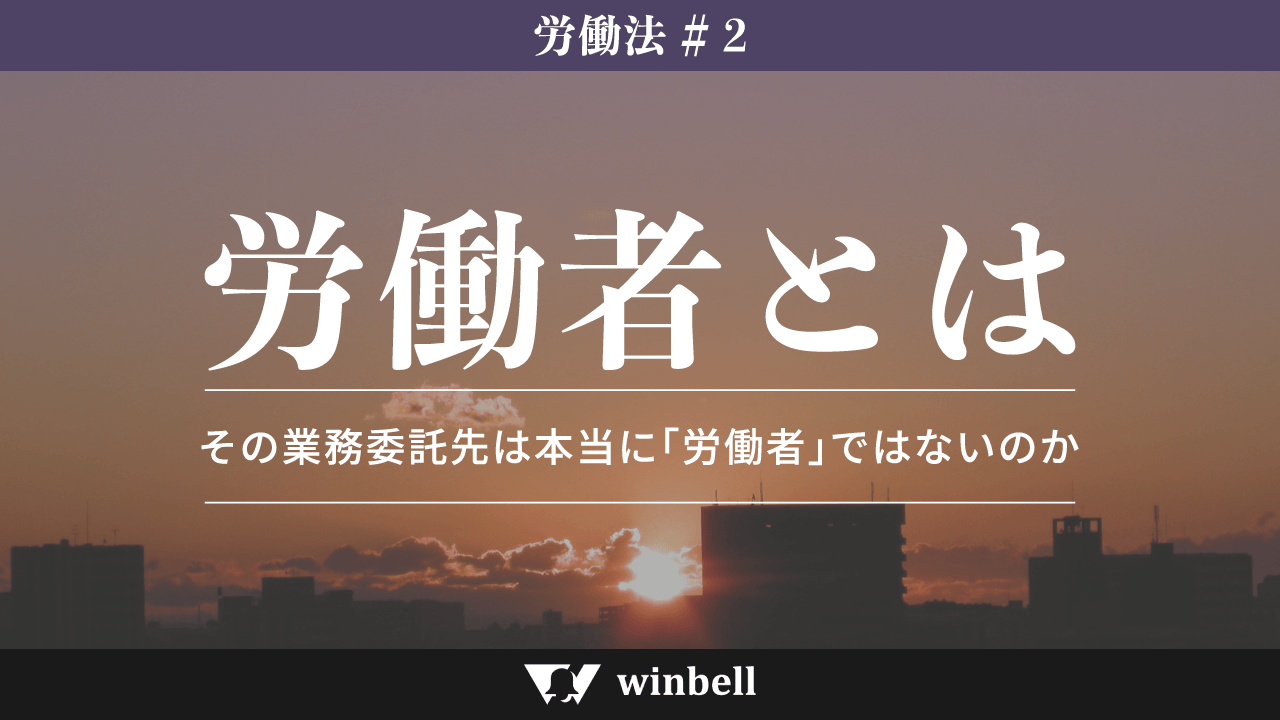
こんにちは。弁護士の山口真彦です。
さて、本日から具体的な労働法の中身に入っていきたいと思います。
労働法はなんのためにある?
早速ですが、労働法は何のためにある法律でしょうか?
当然ですが、皆さんのイメージ通り、主には労働者と会社等の労働関係を規律するためにあります。
しかし、現在では、会社で働くスタイルも多様化しており、会社の仕事をする際に「雇用」ではなく、「請負」と「委任」という形で働いている方も多くいらっしゃると思います。
特に最近では、システムエンジニアの方が「雇用」ではなく、業務委託(請負)で仕事をされているケースも多々あると思います。
このように、労働法は、当然ですが「労働者」に適用されるわけですが、世の中には形式的には「労働者」ではない方々がいらっしゃいます。
そうすると、会社側からすると、じゃあ、働いてくれる人とは、「労働契約」「雇用契約」を締結せずに、全員「業務委託契約」にすれば、その人は「労働者」ではないから、労働法の各種ルールを適用しなくていいじゃん!となるかもしれません。
つまり、労働時間の制約はなくなるし、労災保険にも入れなくていいという状況になるかもしれません。
しかし、このように形式的に契約書のタイトルを変えただけで、労働法が適用されなくなるなんておかしな話ですよね。
ですから、法律は、このような形式的な判断で「労働者」か否か、つまり労働法が適用されるかどうかを判断することはありません。
会社側からすると、「この人とは、業務委託契約だから。」という理由で、めちゃくちゃ働かせたり、労災保険に入れなかったりすると、あとから、「いや、この人は労働者ですよ。」と言われる可能性があり、大きなリスクを負うことになります。
そこで、今回は、「労働者」はどのように判断されるのかを皆さんに学んでいただきたいと思います。
今日の話を踏まえて、もし、自社のために労力を注いでくれている人の中に、業務委託契約の方がいれば、もう一度見直していただき「労働者」に本当に該当しないのかを確認してください。
労働者の定義
まずは、法律がどのように「労働者」を定義しているか確認しましょう。
たとえば、労働契約法は次のように規定しています。
「労働者」=「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」です。労働基準法にもほぼ同じ内容で規定されています。
さて、これだけではちょっと判断できないですよね?そこで、この定義を2つの要素に分解したいと思います。
労働者の定義の2つの要素
1つ目は、「①使用される」、2つ目は、「②賃金の支払い」です。
まずは、①使用されるという点ですが、これは、会社側の指揮命令下で労務を提供するという意味です。
次に、②賃金は、労働の対価として会社が労働者に対して支払うすべてのものという意味です。
ようは、労働者とは、会社から指揮命令を受けて、その通り働き、その対価として賃金を得る人ということです。
もう少し具体的に解説します。
労働者か否かの判断をする際に、一般的によく使われている判断要素がありますので、そちらを紹介します。
- ①仕事の依頼への諾否の自由があるか否か
- 労働者は自由はない。
- ②業務遂行上の指揮監督
- 労働者は指揮監督を受ける。
- ③時間的・場所的拘束性
- 労働者は拘束される。
- ④代替性
- 労働者は代替性はない。
- ⑤報酬の算定・支払方法
- 労働者は報酬の算定が時間単位や日単位である(出来高制ではない。)。
この5つの要素が「労働者」か否かを判断する主要な要素になります。
さらに、これらの要素に加えて、労働者性を補強する要素として、
- 使用する機械や器具の負担の有無
- 報酬の額
- 専属性の程度
などの要素も加味して判断していきます。
一言で「労働者」と言ってもその判断は非常に難しい
以上のように、一言で「労働者」と言ってもその判断は非常に難しい点があります。
経営者としては、まずは、契約書が「業務委託契約書」になっているからその人は労働者ではないと安易に判断しないことが重要です。
そして、契約するときにどのような働き方を会社が希望しているのか、どのような条件を提示するのかをしっかり確認した上で、労働者に該当することはないのか、該当する場合は、各種労働法の規制を守る必要が出てくることを理解しておきましょう。
特に、最近は、IT業界において、「偽装請負」という問題も生じています。
「偽装請負」については、YouTubeなどの別の機会で解説したいと思いますが、注意が必要です。
それでは、本日は以上です。